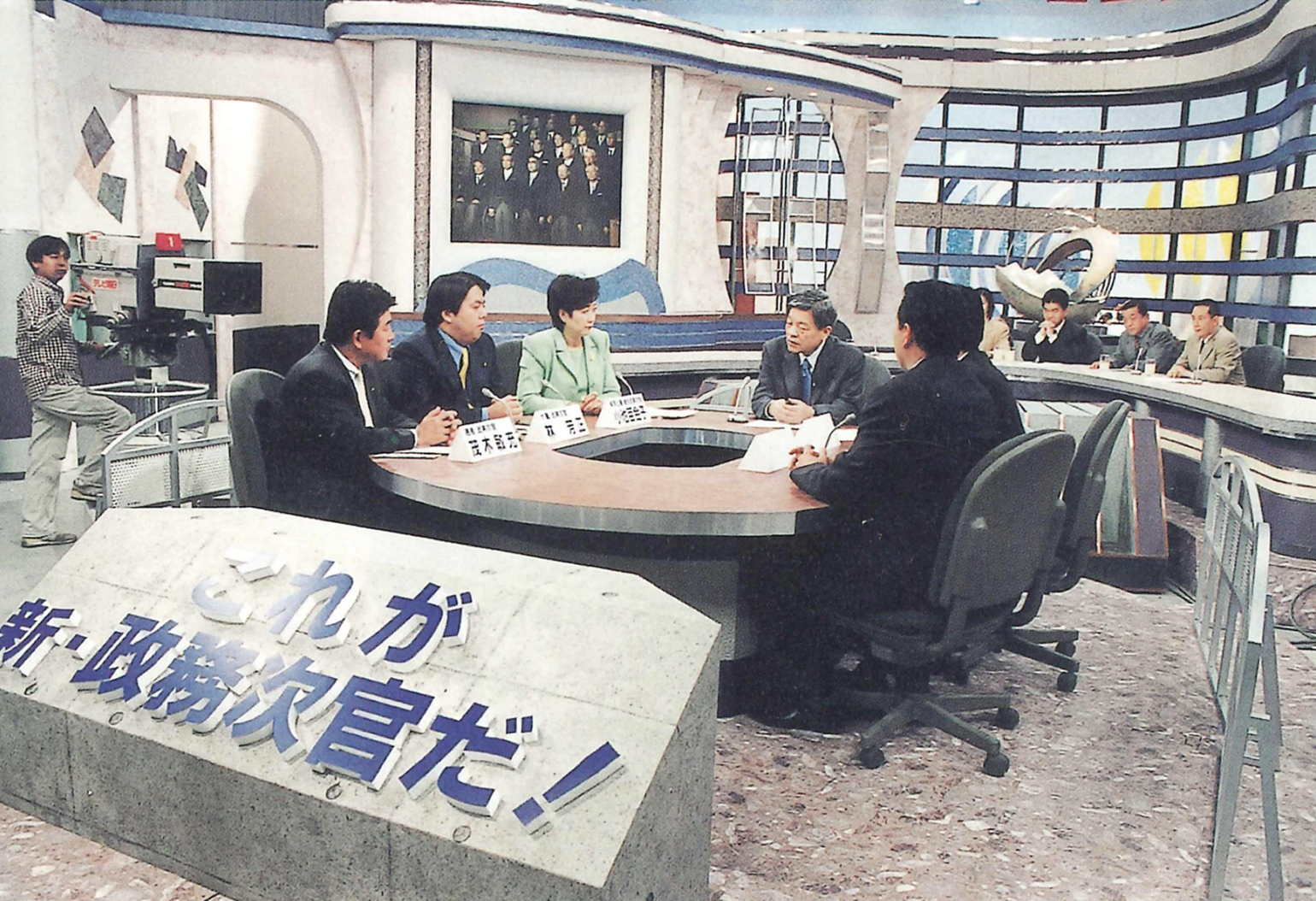2023年
内閣官房長官
2021年
外務大臣
2019年
文部参議院憲法審査会 会長
知的財産戦略調査 会長
量子議連 会長
日中友好議員連盟 会長
税制調査会 小委員長代理
経済成長戦略本部 座長
IT戦略特別委員会 委員長
宏池会 座長
2018年
税制調査会 小委員長代理
経済成長戦略本部 座長
IT戦略特別委員会 委員長
宏池会 座長
日中友好議員連盟 会長
2017年
文部科学大臣
2016年
参議院環太平洋パートナーシップ協定等
に関する特別委員会 委員長
2014年
自民党 農林水産戦略調査会会長
税制調査会副会長
2011年
自民党シャドウ・キャビ ネット官房副長官
自民党政務調査会長 代理(留任)
2010年
自民党シャドウ・キャビ ネット官房副長官
自民党政務調査会長 代理(留任)
自由民主党財務金融部会会長
2008年
防衛大臣
2007年
参議院予算委員会筆頭理事
2004年
外交防衛委員会 委員長
2003年
個人情報特別委員会 理事
予算委員会 理事
2000年
選挙制度に関する特別委員会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
決算委員会
財政・金融委員会 理事
政治倫理の確立及び公職選挙
法改正に関する特別委員会
1999年
大蔵政務次官
1998年
財政・金融委員会
議院運営委員会
行財政改革・税制等に関する特別委員会
経済活性化及び中小企業対策に関する
特別委員会 理事
参議院予算委員会 理事
1997年
行財政改革・税制等に関する特別委員会
国際問題に関する調査会
自由民主党参議院副幹事長
1995年
議院運営委員会
商工委員会
国際問題に関する調査会
1994年 
衆議院議員林義郎政策秘書
1993年 
林義郎大蔵大臣政務秘書官